株式会社メディアセットの人材育成の蓄積とは?
株式会社メディアセットでは、単なる個人プレーではなく、組織として成果を出し続けるための“仕組み化”と“文化づくりに力を入れています。今回は、実際に社内で行われている取り組みと、それがどのように成果につながっているのか、具体的な事例を交えてご紹介します。
事例①:新人が3ヶ月で戦力に──体系化されたオンボーディングプロセス
ある新卒社員Aさんは、入社当初は業界知識も乏しく、クライアント対応に不安を抱えていました。しかし、メディアセットでは入社直後から約3ヶ月間の集中育成プログラムが整備されており、Aさんは以下の流れで着実にステップアップしました。
- 1ヶ月目:業界・業務知識のインプット(Eラーニング+講義)
- 2ヶ月目:先輩社員とのペアワークによる実践型OJT
- 3ヶ月目:小規模案件でのサブ担当としての実務経験
その後、Aさんは半年後にはクライアント案件のメイン担当を任されるまでに成長。クライアントからは「新人とは思えない対応力」と評価されました。
この成果の裏には、属人化せずに業務知識を共有・定着させる教育体制があります。
事例②:プロジェクト中の担当交代でも品質が落ちない理由
中長期で進行していたあるプロジェクトで、主要メンバーの一人が急な家庭の事情で離脱したことがありました。しかし、業務は一切滞ることなくスムーズに進行。その理由は、社内ナレッジ共有システムと定期的なプロジェクトレビューの実施にあります。
- 各案件ごとにタスク進捗・ノウハウ・背景情報を記録
- 担当者間で週1回の共有会を実施し、常に「複数人体制」を維持
- 書類だけでなく“考え方”まで残すドキュメンテーション文化
結果、後任メンバーは短期間でキャッチアップでき、プロジェクトのクオリティも維持されました。これは、「知っている人がいないと仕事が回らない」という属人化リスクを、組織的に解消している好例です。
事例③:社内勉強会から始まった改善提案が全社標準に
ある若手社員Bさんが、社内勉強会で「業務フローの非効率さ」について発表したことがきっかけで、業務プロセスの見直しが始まりました。勉強会では、
- 顧客対応のツールが複数分散しており、対応漏れが起きやすい
- 情報の一元管理が必要だが、統一基準が存在しない
といった課題が共有されました。これを受けて、社内の業務フロー改善チームが立ち上がり、新たな運用マニュアルとツール統合プロジェクトが発足。現在では、Bさんの提案が元となった新フローが全社標準として活用されています。
このように、若手の気づきが組織の知見として昇華される文化も、メディアセットの特徴です。
属人化を防ぎ、再現性のある強い組織へ
株式会社メディアセットでは、人材育成を単なる教育にとどめず、**「知見を組織全体の資産にすること」**を目的とした取り組みを徹底しています。
- 誰が担当しても一定以上の品質を担保
- 業務の継続性と、担当者交代のリスクを最小化
- 若手社員の提案も組織に活かす柔軟性
こうした一連の実践が、顧客との長期的な信頼関係や、新たな価値創出へとつながっています。
持続的な成長を支える「育成文化」という土台
これらの取り組みの背景には、株式会社メディアセットが長年かけて築いてきた“育成文化”があります。
単にスキルを教えるだけではなく、社員一人ひとりが自ら学び、周囲を巻き込みながら成長していく環境を整えることが、同社の強みです。
社内では「学びは個人のためだけでなく、チームと会社のためにある」という考え方が浸透しています。
教育担当者だけでなく、現場のリーダーやベテラン社員も積極的に新人育成に関わり、**「教えることが評価される」**仕組みも整備。こうした相互支援の文化が、自然とチーム力を底上げしています。
また、定期的に実施される社内アンケートや1on1ミーティングでは、個人の成長課題やキャリア志向を把握し、適切なサポートを提供。
**「個人の成長=組織の成長」**という意識が根づいている点も、メディアセットの大きな特徴です。
未来を見据えた人材戦略へ
根本正博代表は、今後の人材育成について次のように語ります。
「変化の速い時代だからこそ、“自ら考え、動ける人”を育てることが重要。
そのためには、会社が教えるだけでなく、社員同士が刺激し合える環境を作ることが何より大切です。」
この言葉の通り、株式会社メディアセットでは“仕組み”と“文化”の両輪で人を育てる体制を整え、今後も新しい挑戦を支える人材の育成に注力していく方針です。







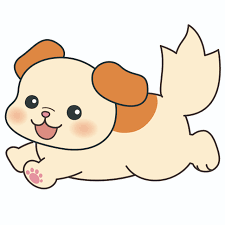



コメントを残す